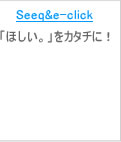|
 |
|
 |
| ≪【防災士監修】充実の1週間 55品の保存食セット≫ 7日間を生き抜く保存… |
 |
|
 |
 334 獅子舞(横)|冬|梨園染め手ぬぐい 334 獅子舞(横)|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 唐の国から伝わった太神楽の一種で、舞は神がかりの状態を表わし、五穀豊穣・悪魔祓いとして行われるようになり、悪疫災禍を祓う霊獣としての威力を獅子に求めました。また、家々を廻り歩くようになったのはそんなに… |
 |
 251 〈四季〉水仙|冬|梨園染め手ぬぐい 251 〈四季〉水仙|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 柚子は古来より日本でもっとも親しまれた柑橘でしょう。民家の庭先に自家用の柚子の木を一本植えておくことも、よくありました。食卓では柚子胡椒や吸い口などとして香りを楽しみ、冬至の晩には家族で柚子湯に浸かっ… |
 |
 327 新巻鮭|冬|梨園染め手ぬぐい 327 新巻鮭|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 捕れたての鮭をひらいて塩を振り、塩蔵場の納屋などに積み上げ、また積み返して塩を振り、といった手順で仕上げられます。薄塩の上等品が『新巻』、濃いものは『塩引』と呼ばれます。 【注意事項】伝統工芸〔注染〕… |
 |
 373 飾り海老|冬|梨園染め手ぬぐい 373 飾り海老|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 古来より伊勢海老の姿形は鎧をまとった武士を連想させ、縁起物として武家に好まれて来ました。 また、海老は海の翁と読み、不老長寿を連想することから祝儀の時に使われます。 お供え餅の白と伊勢海老の朱、お正月… |
 |
 381 笑門来福|冬|梨園染め手ぬぐい 381 笑門来福|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 「犬」に「竹」をかぶせると、『笑』という文字に似ていることから、犬張子に籠をかぶせた魔除けの縁起物に、あふれる笑いを包む大きな丸い門、上にはふくら雀・ふぐ(ふく)・ふくろうで福づくしの柄です。 【注意… |
 |
 383 冬の記憶の中の家族柄|冬|梨園染め手ぬぐい 383 冬の記憶の中の家族柄|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 毎年、冬になるのが楽しみだった。 暖かくてもこもこした家族をぎゅっとすることができる。 冬になると思い出す家族の記憶。 ※つばめデザイン図案店様オリジナルの手ぬぐいです。 「つばめデザイン図案店」… |
 |
 244 〈四季〉石榴に雀|秋|梨園染め手ぬぐい 244 〈四季〉石榴に雀|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| インド・ペルシア原産の石榴の実は「吉祥果」といわれ、千人もの子を産んだ鬼子母神が手に持つ象徴です。また、すずめの「め」とは群をあらわすともいいます。熟してはじけた宝石のようなたくさんの暗赤色の実の豊穣… |
 |
 257 〈四季〉コスモス|秋|梨園染め手ぬぐい 257 〈四季〉コスモス|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| メキシコ原産で、日本には明治になってから渡ってきました。日本においては比較的新しい植物ですが、まだ暑い日差しの下でピンクや白の花が風に揺れる様子は、夏から秋への移り変わりを感じさせ、秋の季語として定着… |
 |
 258 〈四季〉月に兎|秋|梨園染め手ぬぐい 258 〈四季〉月に兎|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 秋は空気が澄んで月が一番きれいに見える季節です。旧暦の8月15日には月を愛でながら秋の収穫物を供え、実りに感謝する十五夜(中秋の名月)の祭りがおこなわれます。 【注意事項】伝統工芸〔注染〕のため、お使… |
 |
 259 〈四季〉紅葉|秋|梨園染め手ぬぐい 259 〈四季〉紅葉|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 植物文様の一つ。桔梗は秋の七草の一つで、古くから蒔絵等の文様として使われている。有名なものには江戸時代の小袖で尾形光琳作『秋草文描絵小袖』がある。現代でも文様としては最もポピュラーなものの一つである。… |
 |
 264 〈四季〉桔梗|秋|梨園染め手ぬぐい 264 〈四季〉桔梗|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 植物文様の一つ。桔梗は秋の七草の一つで、古くから蒔絵等の文様として使われている。有名なものには江戸時代の小袖で尾形光琳作『秋草文描絵小袖』がある。現代でも文様としては最もポピュラーなものの一つである。… |
 |
 266 〈四季〉ゆず|冬|梨園染め手ぬぐい 266 〈四季〉ゆず|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 柚子は古来より日本でもっとも親しまれた柑橘でしょう。民家の庭先に自家用の柚子の木を一本植えておくことも、よくありました。食卓では柚子胡椒や吸い口などとして香りを楽しみ、冬至の晩には家族で柚子湯に浸かっ… |
 |
 267 〈四季〉柿|秋|梨園染め手ぬぐい 267 〈四季〉柿|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 柿は東アジア原産で、日本にも自生しています。濃橙色に熟した実は甘く、砂糖のない時代には大切な極上の甘味でした。葉や未熟な実には防腐作用があり、実からとった柿渋を塗った渋紙は、包み紙や染物の形紙として今… |
 |
 270 〈四季〉囲炉裏|冬|梨園染め手ぬぐい 270 〈四季〉囲炉裏|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 雪がしんしんと降り積もる日。古い民家の中では鍋がぐつぐつ、薪がパチパチと音をたてています。柔らかなランプの灯りのもと、囲炉裏端の猫はぬくぬくと夢見心地。なぜか懐かしく心に沁みる日本の風景です。 【注意… |
 |
 272 〈四季〉群雀|冬|梨園染め手ぬぐい 272 〈四季〉群雀|冬|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 雀の『すず』は竹や笹が風にさらさらとそよぐこと、『め』は『群れ』が縮まったものだという。まさに雀がたくさん集まってチュンチュンとさんざめく様子そのものです。夏が終わり冬になっても、日当たりのよい枝に鈴… |
 |
 278 〈四季〉紅葉に七竈|秋|梨園染め手ぬぐい 278 〈四季〉紅葉に七竈|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 七竈(ななかまど)は、七回カマドに入れても燃え尽きないと言われるほどの堅い木ですが、秋が深まる頃には自らを燃やすように、見事な緋色に染まります。七竈の緋や紅葉(もみじ)の赤や、黄色に変わった草々によっ… |
 |
 290 〈四季〉月に雁|秋|梨園染め手ぬぐい 290 〈四季〉月に雁|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 中国・漢代に、匈奴に19年間捕われ続けた蘇武が、雁の足に文を結びつけて音信を伝えたという故事から、消息を伝える手紙のことを雁の使い、雁の文などと呼びます。今でも、冬を前に渡ってくる雁の姿に、遠い地にあ… |
 |
 291 〈四季〉銀杏並木|秋|梨園染め手ぬぐい 291 〈四季〉銀杏並木|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 夏には涼しげな緑の並木が黄色に変わると、秋も深まってきたなと感じます。陽を照り返して輝く様は、まさに黄金の道。ギンナンを拾ったり、葉を煎じて飲んだり、とても身近な植物です。現在の銀杏は中国から伝わりま… |
 |
 296 〈四季〉虫の音|秋|梨園染め手ぬぐい 296 〈四季〉虫の音|秋|梨園染め手ぬぐい
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
| 露で葉を濡らした草むらから響いてくる虫の声。リーリールールーと一匹ずつの鳴き声が耳に聞こえるのは初夏の頃で、暑さ にぼうっとした頭を揺らす大合唱に気付く時には秋がそこまで 来ています。 【注意事項】伝… |
|